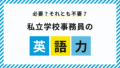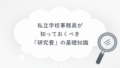この記事は以下のような人を対象としています。
・「学校って、学費や補助金収入だけで経営的に本当に大丈夫なの?」と思っている人
私立学校に限らず民間企業に勤める場合でも、自分の勤め先の主な収入源について理解しておくことは大切です。
金額はもちろんのこと、その収入がどのようなルートから入ってくるのかといったことなども、知っておくべきと思います。
その点から考えると、私立学校はわかりやすい。
- 学生生徒等納付金:生徒、保護者
- 補助金:国、地方公共団体
- 検定料:受験生
この3つをおさえておけば、収入の9割方は理解したも同然です。
しかし、この3つほどの金額的インパクトはないことが多いですが、私が重要と考える収入が他に3つあります。
その3つとは以下のとおりです。
- 寄付金収入
- 付随事業収入
- 受取利息・配当金収入
この3つをいかに増やして「恒常的」な収入にするかというところが、今後の学校運営のポイントになると思います。
「収入の多角化」がキーワードです。
おそらく、すでに私立学校にお勤めの方にとってはわかりきっている内容とは思いますが、これから私立学校事務員を目指す方などは、学校選びの一つの物差しとして参考にしていただければと思います。
【信頼・ロイヤリティのあかし】寄付金収入
1つ目は寄付金収入です。
これについては、以前の記事でも取り上げましたので、そちらの記事も参考にしていただければと思います。
その際は、寄付金の会計処理をメインに解説しましたが、今回は「重要性」について述べたいと思います。
というのも、私が色々な学校法人の決算書等を見てきた中で、収入全体に占める寄付金収入の割合が高いと感じる学校法人は学生生徒等の募集もうまくいっているというイメージがあるからです。
その傾向は、同じ学校法人が設置する学校間でも見ることができます。
例えば私の以前の勤め先は、複数の種類の学校(小学校や高校、大学など)を設置していました。
そのうち、寄付金の割合が他の設置校より高い学校は、前述のとおり募集がうまくいっており、逆に寄付金の割合が低い学校は、募集に苦戦している状況でした。

「この学校になら寄付をしてもいい」と保護者に思われるような学校は、そもそも「この学校に通わせたい」と思わせるだけの力があるということなのでしょうね。
つまり、「どうすれば寄付金をもっと集められるか」は「どうすれば寄付をしたいと思われる学校になれるか」とも言い換えられるということです。
これは高校で言えば、単純に「国公立大学への進学率を上げる」とか「有名私立大学への進学率を上げる」といった話ではないと思います。

現に私の以前の勤め先でも、こうした進学実績と寄付金額との相関関係は、明確には見受けられませんでした。
もちろん、偏差値が極めて高い高校などでは、こうした進学実績に期待して入学していると考えられますので、一概には言えません。
また、寄付金は生徒や保護者からだけ募るものではありません。
私たち事務員も含めた教職員や卒業生、地元企業などにも寄付を募集します。
自分から見て、今の勤め先またはこれから勤めようとしている学校に寄付をしたいと思いますか?
「寄付をしたい」若しくは「寄付したくない」と思った理由を書き出してみてください。
そして、「寄付したくない」理由から「こんな学校だったら寄付してもいい」と思える理想像を考えてみてはいかがでしょうか。
その理想像を目指して、自分ができることに少しずつ取り組めば、多少仕事が楽しく感じられると思います。
寄付金収入の割合を、「その学校に対する信頼やロイヤリティのバロメーター」として捉えて、この割合をどうすれば増やせるかという観点から、日々の業務を見直すきっかけをつくる。
そういったところから金額的な意味以上に「重要」な収入だと考えています。
【副業的存在】付随事業収入
2つ目は付随事業収入です。
多くの人にとってはあまり聞きなれない単語ではないでしょうか。

ここでは一旦、学校法人の「副業」の収入とイメージしていただければ十分です。
この収入科目の重要ポイントは「収支構造の違いを理解すること」になります。
どういうことかと言いますと、収入全体に占める「付随事業収入」の割合がかなり高い学校法人があるということです。
最も顕著な例として「附属病院を持つ学校法人」が挙げられます。
附属病院が日々の診察で受け取る収入は、この「付随事業収入」の1つである「医療収入」として取り扱われ、決算書等に記載されます。
このことを知らずに附属病院を持つ学校法人の決算書を見てしまうと、その学校法人の経営状況を誤解してしまう可能性が生じるわけです。

極端な話、学校の経営が芳しくない状態でも、病院の方の経営が好調であれば、学校法人全体の経営状況がよく見えてしまうかもしれません。
そんな勘違いをしたまま、そこで学校事務員として働き出したら「あれ?」と思うかもしれないということです。
こういう時の対策としては、決算書を図に変換してみることをおすすめします。
それについては、以下の記事をご参照いただければと思います。
この方法で、通常の学校法人の収支状況を「型」として把握しておくことで、通常とは異なる「型」を見た時に、その違いに気づくことができます。
「付随事業収入の割合の高さ」は、その「型」の違いを理解するために重要なポイントの1つですので、おさえておきましょう。
あわせて、病院を設置していないにも関わらず「付随事業収入」の割合が高い「型」をしている学校法人があれば、何かしら「副業的なもの」を行っている可能性があります。
その学校法人を参考にして、自分の勤め先でも取り組むことはできないか考えてみるのも「収入の多角化」につながると考えています。
【収入多角化の代表】受取利息・配当金収入
最後は受取利息・配当金収入です。
文字通り、預貯金口座から得られる利息などがここに分類されます。
昨今は、個人向けの資産運用が話題になっていますが、今から10数年前は学校法人の資産運用というものがよく取り上げられていたように記憶しています。

雑にとらえれば、サラリーマンと学校法人の収入構造は似ているのかもしれません。
- サラリーマン:ほぼ給与収入のみ
- 学校法人:ほぼ学生生徒等納付金収入のみ
だから、「収入の柱を増やそう」ということで、資産運用を始めるケースが増えたのかなと思っています。
学校法人のケースでは、その後にサブプライムローン問題等による金融危機が発生。
多額の含み損を抱える学校法人について、マスコミなどが報道し、大きな問題となったということがありました。

その後の経過を観察していましたが、この資産運用が原因で破産まで至ったような学校法人はなかったように認識しています。
結局、満期まで保有していたら元本は返ってくるという金融商品で皆さん運用をしていたのではと推察しています。
また、NISA制度などでも出てくる「非課税」というワードですが、学校法人も所得税法の定めにより、預金の受取利息等については「非課税」となっていますので、豆知識として知っておきましょう。
学校法人は将来の施設設備更新等のために、多額の資金を確保しておく必要があります。
しかし、そうした資金を実際に使うのはかなり先、という場合がほとんどです。
そうなると、そのまま普通預金等で寝かせておくのはもったいないと考えられます。
そこで、検討されるのが金融商品による資産運用というわけです。
なお、資産運用には以下のような特徴があると私は考えています。
- 比較的簡単に着手できる
- 運用の結果が早く確認できる

学生生徒等を増やそうと取り組んでも、急に次年度から生徒が増えるということは滅多にありません。
その点、資産運用は1年単位等で成果が現れるケースがほとんどです。
もちろん、学校法人の「公共性」という観点から、安全性の高い金融商品で運用する必要があることは言うまでもありません。
ただ、短期的にある程度のリスクをとって収入増を図るとともに、中長期的には学生生徒等の増加に取り組むというバランスも、これからの学校法人の経営を考える上では必要ではないでしょうか。
「お金が入ってくるルートの多角化」に加えて「成果が出るまでの時間軸の多様化」という意味もあると思います。
皆さまの頭の片隅にでも意識しておくことをおすすめします。
まとめ
私立学校事務員として働くうえで、自身の勤め先の経営状況を把握することは必須です。
加えて、把握した状況を踏まえて「改善」まで考えられるようになることも求められます。
その改善策を考えるためのポイントの1つとして「収入の多角化」があります。
この記事では、「収入の多角化」を考える際に特に重要と私が考えているものを3つ紹介しました。
「付随事業収入」のようにすぐには取り組めないものもありますが、こうした観点から検討してみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。