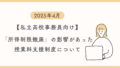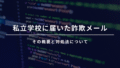この記事は以下のような人を対象としています。
・「40代私立学校事務員としてどうあるべきか」と不安や悩みを抱いている人
皆さんの中で、40代といえばどんなイメージでしょうか。
職場の中堅どころとして活躍しながら、プライベートでパートナーや子どもと過ごす時間も大切にする、忙しいながらも充実した日々を送る姿を思い浮かべるのは私だけでしょうか。
ちなみに私は独身で、職場では一番下っ端の立場ですので、上述のイメージにはかすりもしません。
そんな私でも、やはり「40代らしさ」というものを意識します。
その「40代らしさ」とはどんなものかを知りたく、今回紹介する書籍を手に取りました。
この記事では、その書籍から私が「40代私立学校事務員として特に重要」と感じたポイントを3つ紹介したいと思います。
3つのポイントとは以下のとおりです。
40代がうまくいく人の戦略書より引用
- これまでの経験を「アウトプット」することで、「お金を稼ぐ」ことはできないか P51
- 「40代で新たな資格を取るくらいだったら、自分で資格をつくってしまえばどうか」 P53
- あえて教わる側の立場になる P136
このブログでも何度か触れてきましたが、私立学校事務員は民間企業等の従業員と比べて「変化」の必要性を感じにくい職種だと思います。
民間企業等に勤めている友人などと話をすると、そのことを実感します。
もちろん無理に変化する必要はありません。
ただ、40代の人が仕事で意識すべき「変化」を理解しておくだけでも、これから40代を過ごすうえで意義があると考えています。
40代の方、もしくはこれから40代をむかえようとする方の仕事に対する考え方の参考となれば幸いです。
書籍の紹介
書籍名:40代がうまくいく人の戦略書
著者名:藤井 孝一
出版社:三笠書房
発売日:2025年4月1日
【スペシャリスト】自分独自の資格を設定して、アウトプット重視の行動
書籍の言葉を再掲します。
40代がうまくいく人の戦略書より引用
- これまでの経験を「アウトプット」することで、「お金を稼ぐ」ことはできないか P51
- 「40代で新たな資格を取るくらいだったら、自分で資格をつくってしまえばどうか」 P53
同じような仕事を日々繰り返し行っていると、「このままでいいのか」という不安を感じることがあります。
しかし前述のとおり、私立学校事務員の仕事は変化の必要性を感じにくい。
「今のままでも、問題なくできているからいいか」と考えてしまい、結局そのまま不安をやり過ごします。
一方「このままではだめだ」と思った人も、「じゃあ、何をしたらよいか」と考えた結果、「何かしらの資格を取得する」という行動をとりがちです。

そんな感じで私は仕事関連の資格から、全く仕事に関係のない資格まで様々なものを取得してきました。
危険物取扱者乙種4類なんかも持っています。ガソリンスタンドで働く予定もないのですが。
しかし、仕事の悩みを紛らわせるために資格を取得していたのでは、ただの「資格ホルダー」となってしまいます。
この書籍では、そうしたインプットよりのスタンスからアウトプットよりへとシフトすることをすすめています。
それは、40代は「これができる」という専門性が求められているからです。
「40代は専門性が求められている」という点は、私も同感です。
私立学校事務員の仕事においても、この年代あたりから例えば「補助金業務といえばあの人」といったイメージが定着してくるケースが多いように感じます。
そうした自分の専門性をさらに磨くためには、インプット以上にアウトプットが重要となってきます。 結局、インプットしたことをアウトプットしなければ、自分の知識やスキルを向上させることはできないように思うからです。

教科書を読んだだけでは、テストの点数は上がりにくいです。問題集を解いたり、友達に教えてみたりすることで理解が深まり、テストの結果もよくなるという経験が皆さまにもあると思います。
そのアウトプットをするうえで、ポイントとして挙げられているのが「稼ぐという視点」と「自分で資格を設定」の2点です。
例えば、私だと「学校法人会計検定2級」という資格を勝手に作るという感じでしょうか。

「1級」と設定できないところに私の自信のなさが現れていると思ってください。
「未公認会計士」という資格も思い浮かびましたが、怪しさ満開でしたので却下しました。
この考え方だと、わざわざ新たに資格の勉強をしなくても、いくらでも自分にとって都合のいい資格を取得できます。
そして、この資格を使って何か稼げることはないか探してみるわけです。
noteの販売やyoutubeで学校法人会計基準の解説動画をアップして広告収入につなげるなどが候補として挙げられそうです。

一応、今もこうしてブログを更新しているわけですが、「これで稼いで食っていく」とまでの意識は正直ありません。
とりあえずアウトプットの一環と思って取り組んでいます。
その結果、「稼ぎ」という面では成果はあがっていませんが、自分の知識や経験を文章というかたちにアウトプットすることで、仕事に関する理解が深まったと実感しています。
今後はこのブログ更新の経験も活かして、「自分で稼ぐ」ということを意識しながら仕事にも取り組んでいこうと考えています。
皆さんも、今までの経験から「資格にできそうなもの」や「稼げそうなもの」はないか探してみてはいかがですか。
【生徒が教師】教える側と教わる側のバランス
書籍の言葉を再掲します。
40代がうまくいく人の戦略書より引用
- あえて教わる側の立場になる P136
40代は第一線で現場に立つ一方で、部下の指導にもあたるいわゆる「プレイングマネージャー」として仕事に取り組む機会が多くなると思います。
その点は民間企業も私立学校も同じではないでしょうか。
ただ、徐々に「教える側」の比重が増してくる傾向にあります。
そこで、「教える側」と「教わる側」の両方を同時に経験しやすい40代という時期をフルに活用すべく、あえて「教わる側」に立つことでバランスをとってみましょう。
40代は前述の「専門家」というポジションに加えて、上司と部下の「調整役」としての立場も求められるようになります。
そうした「調整役」として行動するうえで、両方の立場を理解できるようになることは有意義であると考えられます。

「あんな上司は嫌だ」という思いがあれば、逆に「こんな上司が理想的」というイメージも具体的に思い描いて行動できますよね。反対の立場の場合も同様です。
そして、この「教わる側」を経験するのに学校という環境は最適だと考えています。
それは「生徒」という存在があるからです。
40代の事務員からすると、生徒は自分の子どもくらいの年齢差になるという人も多いと思います。
それだけの年齢差があると、育ってきた環境や価値観など様々な点で違いが生じているはずです。
例えばSNS。
今の生徒は、気づいたころから身近なところにスマホがあり、インターネットを利用して情報の収集や発信をすることに慣れているように感じます。

ちなみに私は、2~3年前までガラケーでした。
そうなると、学校アカウントのSNSを運用するにあたって、あえて生徒から教わるというやり方を取ることができます。
実際私は、学校アカウントのX(旧Twitter)の更新を担当していますが、たまに生徒に「こんな感じの投稿がしたいけど、何かいい方法ある?」と尋ねてみたりします。
すると生徒の方も、聞かれたことを嬉しく思ったのか、機嫌よく教えてくれます。
TikTok担当の教員も、自分が担任のクラスの生徒に色々教わりながら運用している様子です。
「教わる側」を体験できることに加えて、生徒とのコミュニケーションにもなり、一石二鳥の方法だと思っていますので、おすすめです。
まとめ
40代私立学校事務員が「専門家」と「調整役」へ変化するための3つのポイント
- 「稼げる」の視点から自分のスキルや知識を棚卸
- 自分独自の資格を設定して、その資格のスペシャリストとして活動
- 生徒を先生にして、「教わる側」を体験し、「教わる」と「教える」のバランスを調整
私が高校生の頃、40代くらいの先生といえばずいぶん大人に見えた印象が残っています。
その先生たちもちょうど教員組織のなかで「専門家」や「調整役」として変化する過程にあったのでしょう。
高校生からすると、それが「大人の印象」に映ったのではと、この書籍を読んで感じました。
40代私立学校事務員の皆さまも、勤め先の生徒たちの目にどのように見えているか意識してみてはいかがでしょうか。
これから40代をむかえる人も、その時に備えて知識や経験を身につけるようにしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
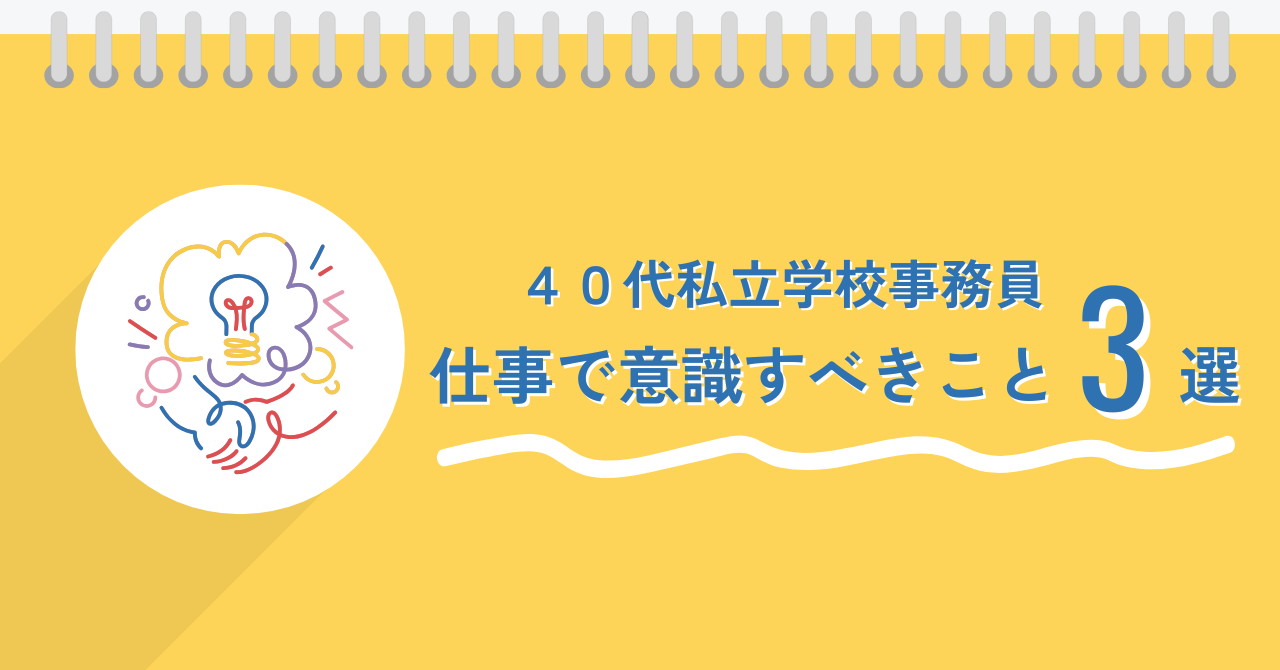
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/429b8c70.55b8a264.429b8c71.7834a660/?me_id=1213310&item_id=21539631&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0357%2F9784837940357_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)