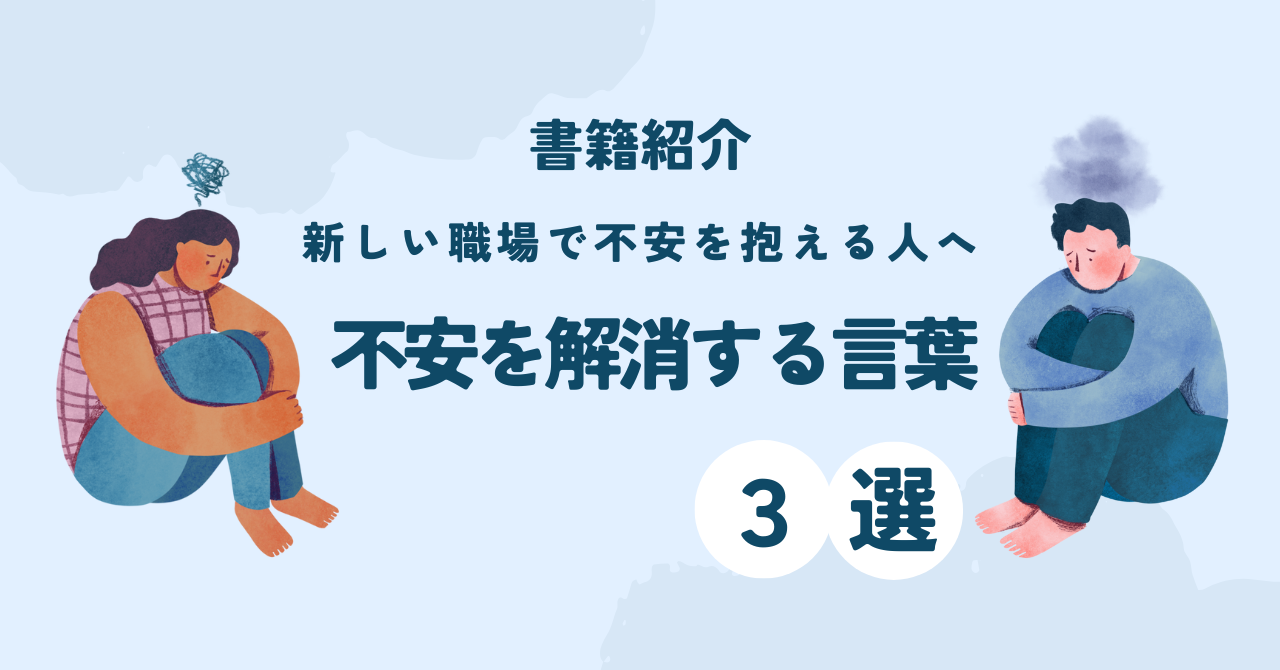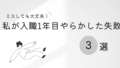この記事は以下のような人を対象としています。
・「自分は新しい職場で本当に役に立つのだろうか」こんな不安な気持ちを払拭したい。
今から約10年前、私はずっと働き続けていた私立学校を退職し、別の私立学校へ転職しました。
初めての転職だったこともあり、当時は相当な不安を抱えていました。
「今までの知識やスキルが役立つのだろうか」「自分は新しい職場でうまくやっていけるのだろうか」こういった思いが頭から離れません。
そんなとき、偶然出会ったのが今回紹介する書籍でした。
ある私立女子高校の校長先生が書いた書籍で、私の次の勤め先である私立高校が「生徒のほとんどが女子」という状況だったので、この本のタイトルを見て「女子生徒とのかかわり方のヒントが書いてないかな」という気持ちで手に取りました。
しかし、読んでみると女子だけに関わらず、現在働いている男性にもあてはまる内容がたくさん書いているのです。
中には、ちょうど当時の私の気持ちにぴったりと合う内容もあり、あっと言う間に読んでしまったことを今でもよく覚えています。
それから月日は経ちましたが、今でも時々この本を読み返す時があります。
そこで今回は、新年度をむかえて当時の私と同じような不安を抱えている人たちに向けた応援の意味を込めて、書籍の中から皆さまのお役に立ちそうな言葉を3つ紹介したいと思います。
その3つとは以下のとおりです。
「働き女子が輝くために28歳までに身につけたいこと」より引用
- 小さいことにくよくよする人は、一方で、周りに配慮することができ、人の気持ちに寄り添える人とも言えます。P71
- 今できることが何かあるでしょう。それをやり続けているうちは、あなたの学校はつぶれない。あなたの心があきらめない限り、大丈夫です。P78
- 組織のなかで人と比べ、自分が劣っているように感じたときも、何かしら自分の果たせる役割は、きっとあるはずです。P88
どの言葉も、今でも私が私立学校事務員として働くうえで大切にしているものです。
皆さまの不安の解消の一助になれば幸いです。
書籍の紹介
書籍名:働き女子が輝くために28歳までに身につけたいこと
著者名:漆 紫穂子
出版社:かんき出版
発売日:2017年11月13日
【対人関係にも有効】短所を長所に「リフレーム」する
書籍の言葉を再掲します。
「働き女子が輝くために28歳までに身につけたいこと」より引用
- 小さいことにくよくよする人は、一方で、周りに配慮することができ、人の気持ちに寄り添える人とも言えます。P71
私も小さいことにくよくよする性格です。

書類を両面印刷でプリントアウトしようと思ったにもかかわらず設定をミスし、片面で大量にプリントアウトしてしまう程度のことでも、「やってしまった」としばらくの間くよくよしてしまいます。
私自身、この書籍を読むまではこの性格が嫌でした。
しかしこの言葉に触れて、「こんな考え方もあるのか」と気づき、考え方が変わったのです。
書籍の別のところで紹介されているのですが、このように「短所を長所に置き換えてみれば」というように考える方法を「リフレーム」と言うようです。
このやり方を知り、自分の「小さなことにくよくよする」という短所を「物事を繊細にとらえることができる」という長所に置き換え、その長所の方を意識するようになったのです。

それからは、小さなミスをしてくよくよしていても、「今日も自分は繊細だなぁ」と楽な気持ちで自分を見ることができるようになりました。
ちなみにこの方法は、他人にも使えることが書籍で紹介されています。
相手の短所と思えるところを、あえて長所に置き換えてみるのです。
書籍では「思ったことをズバズバ言う」という短所を「陰では言わない。サッパリしている」という長所にリフレームするという例が挙げられています。
このように、自分や他人のことを「リフレーム」して見ることができるようになれば、新しい職場でもうまくやっていけるような気がし、転職先への不安が軽減されました。
ぜひ、皆さまも「リフレーム」お試しください。
【やっぱり継続力】小さなことでもできることをやり続ける
ここも書籍の言葉を再掲します。
「働き女子が輝くために28歳までに身につけたいこと」より引用
- 今できることが何かあるでしょう。それをやり続けているうちは、あなたの学校はつぶれない。あなたの心があきらめない限り、大丈夫です。P78
書籍の中では今できることとして「校内を掃除する」「生徒の話を聞く」「数人しか来てくれないかもしれないけど、学校説明会を開催する」などが挙げられています。
これを見て、私は「自分もこれならできる」と思いました。
自分の心の中で無意識に「転職先で大きな結果を出したい」という思いがあったのでしょう。
その思いが自分へのプレッシャーになり、結果「うまくできるかな」という不安につながっていたように思います。
しかし、まずは「今できること」に焦点をあてて、それをやり続けることが大切であるということに気づいたのです。
「小さなことでもできることを一つずつ積み重ねて、周りの信頼を得ること」
これがまず私が転職先で最初のやるべきことだと思ったときに、気持ちが軽くなるのを感じました。
そして、この「自分ができること」を着実に継続することが、学校が永続的に活動することにもつながると考え、そこに集中しました。

まずは「電話対応」と「生徒や教職員へのあいさつ」から取り組んだことを覚えています。
知らず知らずのうちに気負ってしまっていることがあります。
一度立ち止まって、小さなことでもできることを探し、実行することをおすすめします。
【得意・好きに注目】自分の足元を見てポジションを確認する
書籍の言葉を再掲します。
「働き女子が輝くために28歳までに身につけたいこと」より引用
- 組織のなかで人と比べ、自分が劣っているように感じたときも、何かしら自分の果たせる役割は、きっとあるはずです。P88
2番目に紹介した言葉にも近い内容ですが、2番目の方は「新しい環境でもうまく馴染めるかな」といった不安に対する意味合いが強いと思っています。
一方、こちらは自分の能力に不安を感じるときに参考にしたい言葉です。
今までの職場では通用していたスキル等が次の職場でも使えるのか、という不安はどうしても感じてしまいます。

よく「○○(自分の勤め先)の常識は、世間の非常識」というような言葉を聞きます。同じところにずっと勤めていると「この方法は、自分の今の勤め先でしか通用しないやり方ではないのか」と思うことがありますよね。
実は、この不安は私が転職を考えたきっかけにもつながっています。
あるとき、ふと「もし、この学校がなくなって、他の私立学校に転職しても自分はやっていけるのか」という考えが頭をよぎりました。
新卒でずっと同じ私立学校に勤めていたので、それこそ「自分の常識は、世間の非常識ではないか」と不安に思ったわけです。
そこで思い切って転職に踏み切ったわけですが、今度は新しい職場での自分の知識や能力に対する疑問が沸き起こりました。
そんな時に、この言葉が参考になりました。
「仮に自分の知識や能力が劣っていたとしても、何かしら果たせる役割はあるはず」と気持ちを切り替えました。

そして、自分の好きなことや得意なことを思い返してみたのです。
数少ない「好きなこと」や「得意なこと」の中から、今まで積み重ねてきた「経理・会計の知識や経験」と「面倒な作業でも地道にコツコツと最後までやり遂げることができる継続力」にフォーカスして、新しい職場での仕事に臨みました。
結果、お金関係に関する仕事での信頼を得ることができ、新しい職場でも経理・会計業務のほとんどを任せていただけるようになりました。
前の勤め先のやり方に固執するのはよくありませんが、そうした経験の中でも自分の強みなどに結びつくものを見つけて、そこに焦点をあてて行動することを心がければ、不安は軽減されるということをこのときの体験から実感しています。
まとめ
新しい職場での不安を解消する3つのポイント
- 「短所を長所にリフレーム」
- 「できることをコツコツ継続」
- 「小さなことでも得意なことにフォーカス」
前述のとおり、新年度から新しい環境に身を置くようになった方は多いと思います。
そして、半月以上経ってもまだ心の中に不安を抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人も上述の3つのポイントをうまく活用すれば、次第に不安は解消されると思います。
私が実際そうでした。
この内容が、これからの皆さまのお仕事に少しでもお役に立てればと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。